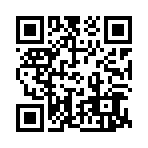2022年03月28日
非鉄金属業界で、産業用ロボットは導入できる
鋳造・ダイカストを効率化したいなら水平・垂直多関節ロボット
一般的に、鋳造作業には、金型の清掃、注湯、取り出しという工程を経る必要があります。これらの工程を効率化し、生産量の増加や生産コストの削減を目指すためには、産業用ロボットを導入することが有用です。
実際に、金型の清掃、溶湯の注入・ハンドリング・冷却等をロボットに行わせることで、生産量を上昇させた事例が有ります。
また、鋳造作業の主要部分は高温環境での重労働作業であり、熟練技を必要とすることが多いです。
それらの人力作業をロボットによる作業へ置き換えることで、安全性の向上や製造工程の不安定化要因の排除することが可能です。
バリ取り・研磨・検査工程を自動化したいなら多関節ロボット
部品加工後に必要となる、トリミング、バリ取り、研磨は、溶融炉のそばの悪環境下で行う場合が多い上、高温の破片が飛び散るため、人力には適さない工程です。
バリ取り工程や研磨工程で、品質の安定化や生産性の向上を図りたい場合には、多関節ロボットの導入がおすすめです。
また、ロボットによる検査生産システムを導入することで、抜き取り検査ではなく完全全数検査が可能になる場合もあります。
----------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはクローズドループステッピングモータとリニアステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
一般的に、鋳造作業には、金型の清掃、注湯、取り出しという工程を経る必要があります。これらの工程を効率化し、生産量の増加や生産コストの削減を目指すためには、産業用ロボットを導入することが有用です。
実際に、金型の清掃、溶湯の注入・ハンドリング・冷却等をロボットに行わせることで、生産量を上昇させた事例が有ります。
また、鋳造作業の主要部分は高温環境での重労働作業であり、熟練技を必要とすることが多いです。
それらの人力作業をロボットによる作業へ置き換えることで、安全性の向上や製造工程の不安定化要因の排除することが可能です。
バリ取り・研磨・検査工程を自動化したいなら多関節ロボット
部品加工後に必要となる、トリミング、バリ取り、研磨は、溶融炉のそばの悪環境下で行う場合が多い上、高温の破片が飛び散るため、人力には適さない工程です。
バリ取り工程や研磨工程で、品質の安定化や生産性の向上を図りたい場合には、多関節ロボットの導入がおすすめです。
また、ロボットによる検査生産システムを導入することで、抜き取り検査ではなく完全全数検査が可能になる場合もあります。
----------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはクローズドループステッピングモータとリニアステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
2022年03月22日
電車を駆動する主電動機の種類
主電動機とは、電車を走らせる駆動用モーターのことです。多くの場合、主電動機は台車枠に取り付けられ、減速機構を介して車輪を駆動します。
主電動機の種類は大まかに直流電動機と交流電動機に大別されますが、構造によりさらに分類すると多くの種類が存在します。本ページでは主電動機の種類や、それぞれの特性の違いについて説明します。
直流電動機と交流電動機
電車の主電動機の種類は、大きく分けると直流モーターと交流モーターに分類されます。それぞれの特徴や構成部品について見ていきましょう。
直流モーターの特徴と構造
直流モーターは、回転子コイルに流れる電流の向きをブラシとコミテータによって切り替えることで、一定の方向に回転しトルクを出力します。
単純に直流電源に接続するだけで回転し、印加する電圧を調整することで容易にトルク制御が可能であるため、主電動機として古くから用いられてきました。
構造上ブラシやコミテータが不可欠なので、摩耗するブラシの交換や摺動部品のメンテナンスに多くの手間がかかります。
交流モーターの特徴と構造
交流モーターは、交流電源に接続することで回転します。交流モーターの可変速制御を行うには交流電源の周波数や電圧を細かく調整する必要があり、パワーエレクトロニクス技術が未発達な時代では鉄道用主電動機としては不向きでした。
現在では、GTOやIGBTなどのパワー半導体を用いたVVVFインバータ装置を用いて、電力を必要な電圧・周波数に変換することで交流モーターを駆動するシステムが主流になっています。
鉄道用主電動機としては、かご型誘導電動機(IM)や永久磁石同期電動機(PMSM)が用いられます。いずれも固定子コイルに三相交流を入力することで回転磁界を発生させることで駆動し、回転子への機械的接点を介した電力供給は行いません。
そのためブラシやコミテータが不要で、直流電動機と比べてメンテナンスフリーな特徴があります。
--------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはハイブリッドステッピングモーターとバイポーラステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
主電動機の種類は大まかに直流電動機と交流電動機に大別されますが、構造によりさらに分類すると多くの種類が存在します。本ページでは主電動機の種類や、それぞれの特性の違いについて説明します。
直流電動機と交流電動機
電車の主電動機の種類は、大きく分けると直流モーターと交流モーターに分類されます。それぞれの特徴や構成部品について見ていきましょう。
直流モーターの特徴と構造
直流モーターは、回転子コイルに流れる電流の向きをブラシとコミテータによって切り替えることで、一定の方向に回転しトルクを出力します。
単純に直流電源に接続するだけで回転し、印加する電圧を調整することで容易にトルク制御が可能であるため、主電動機として古くから用いられてきました。
構造上ブラシやコミテータが不可欠なので、摩耗するブラシの交換や摺動部品のメンテナンスに多くの手間がかかります。
交流モーターの特徴と構造
交流モーターは、交流電源に接続することで回転します。交流モーターの可変速制御を行うには交流電源の周波数や電圧を細かく調整する必要があり、パワーエレクトロニクス技術が未発達な時代では鉄道用主電動機としては不向きでした。
現在では、GTOやIGBTなどのパワー半導体を用いたVVVFインバータ装置を用いて、電力を必要な電圧・周波数に変換することで交流モーターを駆動するシステムが主流になっています。
鉄道用主電動機としては、かご型誘導電動機(IM)や永久磁石同期電動機(PMSM)が用いられます。いずれも固定子コイルに三相交流を入力することで回転磁界を発生させることで駆動し、回転子への機械的接点を介した電力供給は行いません。
そのためブラシやコミテータが不要で、直流電動機と比べてメンテナンスフリーな特徴があります。
--------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはハイブリッドステッピングモーターとバイポーラステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
2022年03月15日
産業用ロボットのプログラミングの命令の種類
移動命令
移動命令とはロボットを指定した位置へ移動させる命令です。主に、
直線補間(始点と終点の2点を指定しておき、始点と終点を結ぶ直線上を動く動作)
円弧補間(中心位置、回転方向、終点の3点を指定しておき、コンパスの要領で円弧を描くように周回する動作)
といった動きを指定することが可能です。
速度命令
ロボットが移動する速度に関する命令です。分速(mm/分)や倍速(%)、加減速時間を指定する命令などがあります。加減速時間などを調整することで、1製品あたりの製造工程にかかる時間(タクトタイム)やワークの停止位置精度を最適化することが可能です。
入出力命令
入出力命令はサーバなどの外部機器とロボットがデータ通信を行うための命令です。入出力命令を駆使することで、ネットワーク接続やBluetoothなどのデータ通信を行うことが可能になるので、工場機器をネットワークで繋ぐ「スマートファクトリー」の施策を推進している工場では特に活躍する命令です。
繰り返し処理命令
繰り返し命令は任意の動作などを一定時間もしくは一定回数繰り返させるための命令です。
分岐・ジャンプ命令
分岐・ジャンプ命令は特定の条件に応じて次の動作を変えるための命令です。たとえば検品作業時に優良品か不良品かによって作業内容を変えたい場合などに活用します。
演算命令
コンピュータプログラミングと同様に、ロボットプログラミングにおいても、四則演算や三角関数などの演算命令が活用されています。このほかに、ロボット特有の演算命令として、ワークの位置データを演算する命令なども用意されています。
その他
ロボットメーカーによっては、塗装やハンドリングなどの専門作業にも対応できるオプション命令を用意している場合もあります。
----------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはギヤードモータとリニアステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
移動命令とはロボットを指定した位置へ移動させる命令です。主に、
直線補間(始点と終点の2点を指定しておき、始点と終点を結ぶ直線上を動く動作)
円弧補間(中心位置、回転方向、終点の3点を指定しておき、コンパスの要領で円弧を描くように周回する動作)
といった動きを指定することが可能です。
速度命令
ロボットが移動する速度に関する命令です。分速(mm/分)や倍速(%)、加減速時間を指定する命令などがあります。加減速時間などを調整することで、1製品あたりの製造工程にかかる時間(タクトタイム)やワークの停止位置精度を最適化することが可能です。
入出力命令
入出力命令はサーバなどの外部機器とロボットがデータ通信を行うための命令です。入出力命令を駆使することで、ネットワーク接続やBluetoothなどのデータ通信を行うことが可能になるので、工場機器をネットワークで繋ぐ「スマートファクトリー」の施策を推進している工場では特に活躍する命令です。
繰り返し処理命令
繰り返し命令は任意の動作などを一定時間もしくは一定回数繰り返させるための命令です。
分岐・ジャンプ命令
分岐・ジャンプ命令は特定の条件に応じて次の動作を変えるための命令です。たとえば検品作業時に優良品か不良品かによって作業内容を変えたい場合などに活用します。
演算命令
コンピュータプログラミングと同様に、ロボットプログラミングにおいても、四則演算や三角関数などの演算命令が活用されています。このほかに、ロボット特有の演算命令として、ワークの位置データを演算する命令なども用意されています。
その他
ロボットメーカーによっては、塗装やハンドリングなどの専門作業にも対応できるオプション命令を用意している場合もあります。
----------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはギヤードモータとリニアステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
2022年03月10日
産業用ロボットの寿命を延ばすコツ
産業用ロボットの寿命を延ばすことはコスト削減にもつながります。少しでも長く使い続けるためには事後保全と予防保全の2つの保全を行うことが大切です。それぞれの保全において、ロボットの寿命を延ばすためにできるコツを紹介します。
事後保全
トラブルが起こってから保全活動を行うことを「事後保全」といいます。少しでも音や動きに違和感が生じたときは事後保全のタイミングと言えるのですが、操作性に問題がない場合は使い続けてしまうケースがあります。しかし、このような行為は産業用ロボットの状態を悪くするだけで、トラブルの深刻化を招く行為でもあります。異音がするなど、トラブルの予兆が見えるときは、すぐに電源を停止して修理専門の業者に依頼しましょう。
予防保全
産業用ロボットの状態に関わらず予防目的で保全活動を行うことを「予防保全」といいます。特に異音などの問題がなくても行うため、早期にトラブルに気付くことができます。しかし、問題がない場所にも保全活動を行うので、余計な時間や手間がかかってしまうこともあります。予防保全は、実施するタイミングによって以下の2つに分かれます。
時間基準保全
一定期間ごとに保全活動を実施することを「時間基準保全」といいます。3か月ごと、6か月ごとと期間を決めておくため、前もって業者に依頼しやすいです。
状態基準保全
劣化や異常のサインが見えたときに保全活動を実施することを「状態基準保全」といいます。サインが見えてから保全活動を行うため、時間基準保全よりは保全活動の回数が少なくて済むことが多く、また、不必要な部位には保全活動を行わないため無駄が少ないというメリットがあります。
しかし、こまめに産業用ロボットの状態をチェックしないと保全の基準を満たしているか分からないので、センシング技術等を活用した自動監視システムなどの導入も検討が必要です。
---------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはハイブリッドステッピングモーターと遊星ギアボックスモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
事後保全
トラブルが起こってから保全活動を行うことを「事後保全」といいます。少しでも音や動きに違和感が生じたときは事後保全のタイミングと言えるのですが、操作性に問題がない場合は使い続けてしまうケースがあります。しかし、このような行為は産業用ロボットの状態を悪くするだけで、トラブルの深刻化を招く行為でもあります。異音がするなど、トラブルの予兆が見えるときは、すぐに電源を停止して修理専門の業者に依頼しましょう。
予防保全
産業用ロボットの状態に関わらず予防目的で保全活動を行うことを「予防保全」といいます。特に異音などの問題がなくても行うため、早期にトラブルに気付くことができます。しかし、問題がない場所にも保全活動を行うので、余計な時間や手間がかかってしまうこともあります。予防保全は、実施するタイミングによって以下の2つに分かれます。
時間基準保全
一定期間ごとに保全活動を実施することを「時間基準保全」といいます。3か月ごと、6か月ごとと期間を決めておくため、前もって業者に依頼しやすいです。
状態基準保全
劣化や異常のサインが見えたときに保全活動を実施することを「状態基準保全」といいます。サインが見えてから保全活動を行うため、時間基準保全よりは保全活動の回数が少なくて済むことが多く、また、不必要な部位には保全活動を行わないため無駄が少ないというメリットがあります。
しかし、こまめに産業用ロボットの状態をチェックしないと保全の基準を満たしているか分からないので、センシング技術等を活用した自動監視システムなどの導入も検討が必要です。
---------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはハイブリッドステッピングモーターと遊星ギアボックスモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。